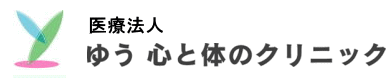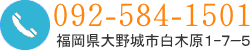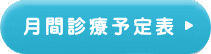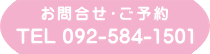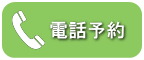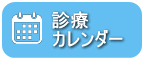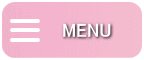自立支援医療制度
(精神通院医療制度)
~通院費の負担を軽減できる公的制度です~
心の不調で、通院やお薬の治療が長く続くと、経済的な負担が心配になる方も多いかと思います。そんなときに利用できるのが、「自立支援医療(精神通院医療)」という制度です。
この制度を利用することで、精神科・心療内科への通院費やお薬代などが原則1割負担になります(通常は3割負担)。安心して治療を継続するための大切なサポート制度です。
・対象となる方
以下のような心の病気や症状で、継続的に通院治療が必要な方が対象となります。
- うつ病、不安障害、パニック障害
- 統合失調症、双極性障害(躁うつ病)
- 発達障害、強迫性障害
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
など
※医師が必要と判断した場合に申請できます。
・支援の内容
- 通院時の診察代
- 処方箋に基づくお薬代(保険調剤)
- 訪問看護、デイケアなどの一部医療サービス
いずれも、通常3割→原則1割負担に軽減されます。
※世帯所得に応じて月ごとの自己負担上限が設けられているため、高額になりすぎる心配もありません。
・申請の流れ
(簡単3ステップ)
- 自立支援医療の対象かどうかを主治医に確認
- 必要書類の作成(当院でサポート)
診断書の作成や申請書記入をお手伝いします。 - お住まいの市区町村窓口へ提出(当院で代行も可能です)
申請後、通常は1~2か月程度で「自立支援医療受給者証」が交付されます。
・制度を利用することで
- 継続的な治療に対する経済的負担が軽減される
- 精神的にも安心して通院を続けられる
- 通院中断による症状の悪化を防げる
自立支援医療は、「安心して治療を受けられる環境を整えるための制度」です。
・お問い合わせ・申請サポート
制度の詳細や申請書類については、受付または医師にお声がけください。
申請については当院で代行できます。
精神障害者保健福祉手帳
~日常生活や社会参加のための「もうひとつの支え」~
精神障害者保健福祉手帳(以下、「精神保健福祉手帳」)は、うつ病や不安障害、統合失調症、発達障害などで長期的な通院・生活上の困難がある方を対象とした、「生活支援と社会参加のための公的手帳制度」です。
手帳を持つことで、さまざまな支援やサービスを受けやすくなります。
・精神保健福祉手帳の目的
この手帳は、障害があっても安心して社会生活を送れるよう、次のような支援の「窓口」となる制度です。
- 経済的な負担の軽減(税制・交通・公共料金など)
- 障がい者雇用や就労支援(就労移行支援・就労継続支援など)
- 障がい者雇用や就労支援(就労移行支援・就労継続支援など)
- 公共サービスや民間の割引制度の活用
- 各種福祉サービスの利用の際の証明
など
・対象となる方
以下のような精神疾患があり、長期的な治療や生活の制約がある方が対象になります。
- うつ病・双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 不安障害・パニック障害
- PTSD・強迫性障害
- 発達障害(ASD・ADHDなど)
- その他の精神疾患(医師の診断により)
※診断名だけではなく、「生活への影響の程度」が判断材料となります。
・等級と支援内容
手帳には、障害の状態に応じて「1級・2級・3級」の等級があります。
等級により受けられる支援の内容は異なりますが、たとえば次のようなメリットがあります。
主な支援例(自治体や地域によって異なります)
- 所得税・住民税の控除
- NHK受信料の減免
- 公共交通機関の割引(バス・電車など)
- 携帯電話料金や電気料金の割引
- 就労支援施設・障害者雇用への応募資格
- 公営住宅の優先入居
など
※詳細はお住まいの自治体により異なります。申請時にご確認ください。
・申請の流れ
- 医師の診断書または障害年金の証書を準備(当院でサポート)
- お住まいの市区町村(福祉課・障害福祉窓口など)で申請
- 審査のうえ、認定されると手帳が交付されます(約1〜2か月)
・有効期間と更新
- 有効期限は【2年間】です。
- 継続して使用する場合は、有効期限の前に更新手続きが必要です。
・ご相談・申請サポートについて
お気軽に医師またはスタッフにお声がけください。
申請については当院で代行できます。
療育手帳
~発達に特性のあるお子さま・ご本人とご家族を支えるために~
「発達がゆっくりかもしれない」
「知的な遅れや特性があると感じる」
そんなとき、日常生活や学習、社会参加を支援するために利用できるのが、「療育手帳」です。
療育手帳は、知的障害のある方(お子さま・大人)を対象とした公的な福祉制度で、
医療・教育・福祉・就労などのさまざまな支援やサービスを受けやすくする目的で交付されます。
・対象となる方
療育手帳は、以下のような状態にある方が対象となります。
- 18歳未満の場合:
知的な発達の遅れが認められ、今後も支援が必要と見込まれるお子さま - 18歳以上の場合:
知的障害の診断を受けていて、日常生活に配慮や支援が必要な方
※知的障害の程度や日常生活への影響を総合的に判断して、交付されます。
・手帳の等級と区分
(自治体によって呼び方が異なります)
- A判定(重度)
- B判定(中~軽度)
等級に応じて、受けられるサービスや割引内容が異なります。
等級の判断は、発達検査や知能検査(例:WISC、田中ビネーなど)および日常生活の状況などを基に、自治体の専門機関が行います。
・受けられる支援の例
- 通所支援(療育施設・放課後等デイサービスなど)
- 福祉サービス(居宅介護、就労支援施設など)
- 公共交通機関の割引(バス・電車・タクシーなど)
- 各種税制の優遇(所得税・住民税・自動車税など)
- 障害者手帳割引(映画館・美術館・テーマパークなど)
- 特別支援学校や就労支援の利用時の証明
など
※支援内容は自治体によって異なります。申請時にご確認ください。
・療育手帳の申請の流れ
- 自治体の判定機関での面接や検査(1〜2か月程度)
- 審査後、手帳の交付(郵送または窓口交付)
・相談ください
- お子さまの発達に不安がある
- 支援を受けるために療育手帳が必要か知りたい
- 知的障害の診断を受けたが、制度をどう使えばいいか分からない
- 将来のために手帳を取っておいた方がよいか迷っている
療育手帳は、その人の「可能性」を広げるための制度です。
ご本人やご家族の生活がより安心できるよう、一緒に考えていきましょう。
障害年金
~こころの病気でも、生活の支えとなる年金を受け取れる場合があります~
うつ病や統合失調症、双極性障害、発達障害などの精神疾患により、「働くことが難しい」「日常生活に大きな支障がある」という状態が続いている方は、「障害年金」という公的制度の対象になる可能性があります。
「年金」と聞くと高齢者向けの制度と思われがちですが、障害年金は、病気やけがで生活や就労が困難になった方のための制度です。
・障害年金とは?
障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に制限がある方に支給される年金制度で、精神疾患も対象となっています。
受け取れる年金には以下の2種類があります。
- 障害基礎年金(主に国民年金加入者)
- 障害厚生年金(厚生年金に加入していた方)
・受給の条件(主なポイント)
- 初診日の確認ができること
最初に病院を受診した日(初診日)が明確で、保険加入中であったことが必要です。 - 一定の保険料納付要件を満たしていること
初診日の前日に、保険料の納付が一定以上あること。 - 現在の障害の状態が、国の定める基準に該当していること
「日常生活がどれくらい制限されているか」が重要です。
・障害等級について
障害年金は、状態に応じて1級~3級(障害基礎年金は1~2級)に分かれます。
- 1級:常に他人の介助が必要な状態
- 2級:日常生活に著しい支障がある
- 3級:労働が著しく制限される(※厚生年金のみ)
・申請の流れ
- 当院で診断・障害年金用の診断書を作成
- 就労状況等申立書の作成(当院でサポートも可)
- 年金事務所または市町村(年金課)へ申請書類を提出
- 審査後、支給決定が通知されます
当院では、就労状況等申立書の記入など、丁寧にサポートします。
・ご相談・お問い合わせ
障害年金の申請には準備や手続きが必要ですが、生活を安定させる大切な制度です。
当院では、申請に必要な**診断書の作成・通院記録の整理などのご相談も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
特別児童扶養手当
~障がいのあるお子さまの子育てを支えるための制度です~
「発達や行動に心配がある」
「障害と診断され、将来の生活が不安」
そんなご家庭の子育てを経済的に支援する目的で設けられているのが、特別児童扶養手当です。
この制度は、身体や精神に障害のある20歳未満のお子さまを養育している保護者の方に対して、月額の手当を支給する公的制度です。
対象となる方
以下の条件に当てはまる場合、保護者(父母または養育者)に手当が支給されます。
対象の児童
- 20歳未満の子ども
- 身体または精神に中程度以上の障害があると認められること
(例:知的障害、発達障害(ASD・ADHDなど)、精神障害、てんかん、身体障害など)
養育している保護者
- 原則として日本国内に住んでいる父・母またはそれに代わって児童を養育している方
- 児童を家庭で現に監護・扶養していること
- 所得制限を超えていないこと
・所得制限について
手当には、申請者・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限(前年分の所得)が設けられています。詳しくは市区町村の窓口でご確認ください。
・申請の流れ
- 医師の診断書を作成
- お住まいの市区町村役所・福祉課に申請
- 審査・認定後、支給開始
・当院でのサポートについて
当院では、特別児童扶養手当の申請に必要な診断書の作成や制度に関するご相談を随時受け付けております。
・ご相談・ご予約
お気軽にご相談ください。